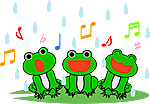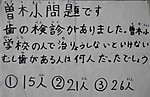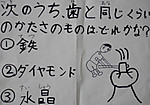『 “ ふるさと学寮 ” でお世話になりました。』・・・その②
3日目の夜は,先生方をお招きして“食事会”を行いました。
メインディッシュは,“ハンバーグ”です。いろいろな具材とミンチ4kgを混ぜ,しっかりこね合わせました。
キャベツのせん切りにも挑戦しましたが,なかなか上手くいきません。![]() でも,一生懸命切りました。
でも,一生懸命切りました。

 みんなで作ったハンバーグの味は,格別でした。
みんなで作ったハンバーグの味は,格別でした。





疲れが出たのか,注意をしっかり受け止めたのか,この日の夜はみんなしっかり寝ていたようです。
さて,このふるさと学寮で何を学びんだでしょうか。家に帰ってから自分の何を変えていけば良いのでしょうか。
地域の方々,子どもたちが本当にお世話になりました。こんな体験ができる子どもたちは幸せです。![]()
![]()
![]() 管理人
管理人 ![]()
![]()